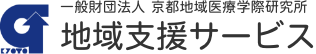訪問看護は、看護師が利用者さんのご自宅を訪問して医療や看護ケアを提供するサービスです。
詳しくは「ご利用までの流れ」をご覧ください。

よくある質問
訪問看護とはどのようなサービスですか?
訪問看護・リハビリを利用するにはどうすればよいですか?
詳しくは「ご利用までの流れ」をご覧ください。
訪問看護の対象となるのはどのような方ですか?
以下のような方々が訪問看護の対象となります。
- 慢性疾患(糖尿病、心臓病、呼吸器疾患等)で継続的な医療管理が必要な方
- 退院後の療養やリハビリが必要な方
- 医療処置(点滴、カテーテル管理等)が必要な方
- 終末期で在宅での緩和ケアを希望される方
- 認知症や精神疾患のある方
訪問リハビリの目的は何ですか?
訪問リハビリの主な目的は以下の通りです。
- 利用者さんの心身機能の維持・回復
- 自立した日常生活の支援
- 生活の質(QOL)の向上
- 社会参加の促進
家族が不在でも訪問してもらえますか?
はい、ご家族が不在でも訪問は可能です。
事前に鍵の管理方法等についてご相談させていただき、安全に訪問できるよう調整いたします。
夜間や緊急時の対応は可能ですか?
定期訪問は月〜金の9:00〜17:00の間で行っております。その他に、24時間いつでも相談ができるシステム(要契約)があります。必要時には訪問も行います。
訪問看護と訪問介護の違いは何ですか?
訪問看護は、医療的なケアや看護を目的としたサービスになります。訪問介護は、日常生活の支援を目的としたサービスになります。
訪問地域は決まっていますか?
訪問エリアをご確認ください。
介護保険に関する事を相談できますか?
「介護サービスを利用したい」「介護の仕方が分からない」など介護保険に関する事をお気軽にご相談下さい。
ご相談内容によって必要な情報、資料を提供させていただきます。
ケアマネジャーは何をする人ですか?
介護支援専門員とは、要介護者や要支援者の人の相談や心身の状況に応じるとともに、サービス(訪問介護、デイサービスなど)を受けられるようにケアプラン(介護サービス等の提供についての計画)の作成や市町村・サービス事業者・施設等との連絡調整を行う者とされています。
(厚生労働省ホームページより引用)
詳細は以下をご確認ください。
相談したいのですが、事業所を訪ねることが困難です。どうすれば良いですか?
来所が困難な場合、お電話で対応させていただきます。
介護認定を受けたいのですが、手続きはどうしたら良いですか?
申請の方法、代行申請の方法などご説明させていただきます。
自宅では相談しにくいのですが、どうすれば良いですか?
事業所の相談室で対応させていただきます。可能な範囲で事前に御連絡頂けましたら相談室の予約をお取りいたします。
地域包括支援センターとはどんなところですか?
地域包括支援センターは、高齢者の方が住み慣れた地域で安心して生活できるよう、京都市が委託運営している公的な相談窓口です。介護、福祉、健康、医療等、高齢者の生活に関する様々なご相談に応じています。
どんな人が利用できますか?
鳳徳学区・紫明学区・出雲路学区にお住まいの高齢者の方とそのご家族、近隣にお住まいの方等、どなたでもご利用いただけます。介護に関する相談だけでなく、健康や福祉、医療に関するご相談も承ります。
相談料はかかりますか?
ご相談は無料です。お気軽にご利用ください。
どのような相談ができますか?
高齢者の方の介護、福祉、健康、医療に関するご相談のほか、認知症や生活の困りごとなどご相談の内容に応じて各専門機関等と連携して支援をおこないます。
介護予防とは何ですか?
介護予防は、高齢になってもできる限り自立した生活を送れるように、心身の機能を維持・向上するための取り組みです。当センターでは、看護師が中心となって介護予防に関する情報提供や教室の紹介等を行っています。
鳳徳・紫明・出雲路学区以外に住んでいますが、相談できますか?
当センターの担当学区は鳳徳・紫明・出雲路学区ですので、お住まいの地域の地域包括支援センターをご紹介させていただくことになります。
認知症について相談できますか?
認知症については当事者の方だけでなくご家族等からも広く相談可能です。ご相談の内容や必要に応じて「京都市認知症初期集中支援事業」等もご紹介させていただきます。
介護保険の申請はどうすれば良いですか?
地域包括支援センターで申請代行をすることも可能です。
相談はどのようにできますか?
電話でも来所でも受け付けています。またご自宅へ職員が訪問させていただき面談することも可能です。
京都市域京都府地域リハビリテーション支援センターはどのような役割を担っていますか?
当センターは、京都市における介護・医療・福祉の連携を促進し、在宅リハビリテーションの推進を図ることを目的としています。リハビリテーションに関する相談対応、訪問指導、研修会の開催、情報発信等を通して、地域のリハビリテーションを支援しています。
どのような相談ができますか?
地域の介護支援専門員、介護職、地域包括支援センター、福祉施設等、在宅介護等リハビリテーションに関わるすべての職種の方から、リハビリテーションに関するアセスメントや技術に関するご相談を承ります。
勉強会や研修会はどのような内容ですか?
維持・生活期のリハビリテーションに関わること等、ご要望に応じてテーマや時間等を設定し、実施いたします。
事例検討会や、在宅や施設で地域リハビリテーションに従事されている方を対象とした技術支援を目的とした研修会等も開催しています。最新の情報はホームページのお知らせ欄をご確認ください。
相談はどのようにすれば良いですか?
電話・FAX・電子メール・相談窓口にて、リハビリテーション専門職であるコーディネーターが直接ご相談を承ります。
センターのコーディネーターはどのような職種ですか?
担当窓口は作業療法士が対応させていただきます。ですが、当センターは京都府リハビリテーション専門職地域人材養成・派遣支援事業に登録してくれている京都市内の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士(2025.4現在 70名)に協力いただいております。
また、京都市内の回復期リハビリテーション病院にも協力病院事業で協力をお願いしておりますので、理学療法士、言語聴覚士に関するご相談も対応可能です。
研修会は誰でも参加できますか?
研修会によって対象者が異なります。詳細については、各研修会のご案内ページをご確認ください。
退院後のリハビリについて相談できますか?
ご相談していただけます。
必要に応じてどんなリハビリテーションが必要なのかを一緒に検討いたしますのでお気軽にご相談ください。
- 注意:現在入院中の医療機関や退院後のかかりつけ医の治療方針が優先となります。
介護をしている家族が、リハビリテーションについて困っています。相談できますか?
当センターは地域の関連職種の従事者への支援センターとなりますので、一般の方やご家族の相談対応は受け付けておりません。支援者の方にご相談の上、ご連絡いただくよう、よろしくお願い致します。
地域の介護事業所ですが、リハビリテーションに関する研修を依頼できますか?
対応させていただきます。どんな研修がご希望かお気軽にご相談ください。
ご要望に応じて協力していただくリハビリテーション専門職種等に声掛けし、実りのある内容になるよう一緒に企画させていただきます。